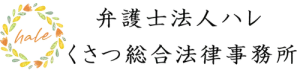Injury
― 傷害・暴行

傷害による刑罰
傷害事件の場合、ほとんどが警察への通報や被害者からの被害届によって捜査となります。
▷ 逮捕の種類
「逮捕」=被疑者が逃げる・証拠隠滅を阻止するため強制的に拘束すること。
つまり、逃亡や証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕することは不要となります。
逃亡や証拠隠滅の危険が無く、被疑者が警察の取り調べに応じるなら、逮捕せずに捜査が進められます。
逮捕には日をまたぐ逮捕令状を伴う逮捕と、窃盗などの現行犯逮捕、犯行直後の準現行犯逮捕、緊急性があり必要に応じて逮捕する緊急逮捕があります。
現行犯逮捕・準現行犯逮捕・緊急逮捕については逮捕令状が不要です。
緊急逮捕の場合は、逮捕したのちに逮捕令状を発付します。
逮捕令状は、裁判官の認定後に発付され、犯行の翌日に警察が自宅に来て逮捕になるケースや、犯行後に捜査の段階で取り調べを受け逮捕になる場合もあります。
1. 現行犯逮捕・準現行犯逮捕
現行犯逮捕・準現行犯逮捕は、警察がその場に居なくても通行人などでも可能です。
その直後に通報などで駆け付けた警察官に犯人を引き渡し、被疑者が取り調べを受けます。
2. 緊急逮捕
緊急逮捕は重大犯罪が発生した際に、必要性があり即逮捕されるものです。
重大犯罪は一般的に、「死刑」「無期懲役」「長期3年以上の懲役」「禁錮刑」などを指します。
指名手配犯が現れた、警察の面前で犯罪が発生などのケースがあります。
逮捕された後
逮捕は被疑者を身体拘束する行為ですので、制限時間があります。
逮捕から起訴まで、身体拘束制限時間は23日間とされ、警察や検察はこの23日間に捜査など調査を行います。
捜査完了後、被疑者が「起訴」されるのか「不起訴」になるのかが決まります。
▷ 逮捕から2日間で
逮捕から検察への送致
▷ 送致後1日で
送致から勾留の請求
▷ 勾留請求~20日間で
勾留起訴決定
起訴から「刑事裁判」
判決結果により「逮捕」
▷ 逮捕から2日間で検察への送致
逮捕後、被疑者は留置場に入り、ここでは「警察」の取り調べを受けます。
逮捕後2日間以内に、警察から検察官に事件を引き継ぐ送致が行われます。
検察官に送致される際は、その日午前、たまたま留置場に居た複数名の被疑者たちと一緒に、警察車両で検察庁へ向かい、複数名の被疑者が順に検察官と面談を行い、その日の夕方警察署へ戻ります。
検察官送致は、原則として全事件で送致されます。被疑者が黙秘していても送致されるのです。
被害が小さく、既に被害側が納得している場合など、「被害者との示談が成立」していれば、検察官送致が発生せず終了となることもあります。
「被害者との示談」とは、金銭による示談もあれば、被害者が刑罰を希望しないなどの示談もあります。
▷ 送致後1日 送致から勾留請求
警察から検察官に送致がなされ、警察から引継いだ証拠と検察官自身による取り調べ後、勾留請求するか決まります。
検察官が「勾留すべきである」と決定すると裁判官に勾留請求をし、裁判官は、裁判所で「勾留質問」を行います。
被疑者から質問の回答を聞き、勾留の判断をします。
検察官が「勾留請求」したとしても裁判官が「勾留しない」場合もあります。
勾留の要件<刑事訴訟法60条1項>
①犯罪の動機
②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか
を満たす場合に認められます。
▷ 勾留決定から20日間 起訴まで
勾留決定の判断が下ると、原則10日間留置場に留置され、最長10日延長が可能です。
勾留中も取り調べや操作は継続されます。
勾留中に家族など面会することは可能ですが、検察官立ち合いが必須で時間制限があります。
検察官は勾留決定から20日間の間に「起訴」「不起訴」の決定を行います。
「起訴」されるということは「刑事裁判にかけられる」ということです。
「不起訴」になるということは「事件が終了するので前科もつかない」ことを指します。
刑事裁判にかけられると、ほとんどの場合有罪となることが多く、「前科」付きから将来を守るためには「不起訴」になることが大切です。
▷ 刑事裁判とは
「不起訴」ではなく「起訴」となった場合、「刑事裁判」となり、「被疑者」ではなく「被告人」として裁判にかけられます。
起訴の種類
① 略式起訴
100万円以下の罰金または科料の場合のみ利用できる略式起訴は、罰金で刑事裁判が終了するが本人の同意が必要
※「過料 (かりょう) 」と「科料 (かりょう) 」の違い
「過料」:行政上の秩序罰=前科は付かない
「科料」:刑事罰で金銭の納付を命じる罰則=「前科1犯」
② 正式裁判略式起訴
起訴されると30日程度で第一回目の公判となります。
被告人が容疑を認めている場合は、2回から4回程度
被告人が容疑を否認している場合は、8回程公判が開かれます。
一般的に審理期間は3か月程度です。
※審理期間とは
起訴から終局までの期間 (公判準備期間を含む)
起訴後に逃亡や証拠隠滅の恐れがある被告人は勾留されます。
この勾留期間に制限はありません。保釈が可能な場合もあります。
刑事裁判で「有罪」になったら
略式罰金:100万円以下の罰金刑や科料(前科1犯)
執行猶予付判決:懲役や禁錮刑に執行猶予が付く
執行猶予期間中に真面目に刑を受けていれば刑務所に入る必要はなくなります。
実刑判決:懲役(労役義務)・禁錮(労役義務無し)で刑務所に入る
上記の有罪となると、前科が付きます。罰金で済んだとしても、前科が付きます。
刑事裁判のほとんどが有罪判決になっている日本で、「無罪」は非常に難しいです。
「有罪」でも、少しでも刑を軽くするために弁護士を雇います。
保釈
逮捕後、「勾留」が決まると、最大20日間の身体拘束を受けます。
「勾留」を回避することが早期保釈には重要です。
逮捕~勾留決定までの3日間に「勾留を防ぐ」ために弁護士を雇います。
起訴後は「保釈」という手続きをとることで釈放される場合もあります。
弁護人を通して「保釈申請」を行い、裁判官が認めた場合、「保釈保証金」を納めることで釈放されます。
「保釈保証金」は被疑者の資産力により150万円~何百万円と差があり、裁判終了後に全額還付されます。
弁護士を雇うと良い理由
勾留が決まると、
長期にわたる身体拘束で被疑者も疲弊し、
早期保釈が難しくなるからです。
▷ 弁護士が主張すること
①罪を犯したと疑う相当の理由
②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)
上記のどれかが該当しないことを主張します。
刑事事件ほど「スピード」が求められるので、刑事事件の弁護士は実績のしっかりある慣れた刑事事件弁護士を雇うことをお勧めします。
弁護士を雇うことで「示談交渉」による事件終了の可能性もあります。
また、逮捕されても「前科」がつかないようにすることで、被疑者の未来を守るお手伝いをします。

傷害事件は逮捕される可能性が高いです。
傷害事件は刑事事件の中でも
逮捕される可能性が高い事件です。
お一人で悩まずに、弁護士に相談しましょう。
傷害事件の費用
一般的に100~300万円ほどと言われていますが、傷害の度合いにより異なります。 傷害を受けた被害者の損害賠償や慰謝料については、ケガや身体の状態、被害者の精神被害などにより異なります。 示談交渉をする際は、弁護士と相談し、相場を知った上でどのくらい出せるか提示した金額で弁護士に交渉を依頼します。
傷害罪と暴行罪
相手にケガをさせた場合、軽いケガでも傷害罪が科せられる場合があります。 傷害とは、中毒や精神被害も含まれ、外的な傷であれ、メンタルの傷であれ、医師の診断書の有無が目安になります。 医師の診断書が無ければ、傷害罪ではなく暴行罪になる可能性が高いです。 また、被害者が軽いケガを、自傷するなど重度のケガとして診察を受け傷害罪を主張する場合もあります。 その場合、弁護士が入ってこの傷害事件で重度のケガになる不合理な点を主張する必要があります。
過失傷害
不注意により被害者にケガをさせた場合は過失傷害になります。 業務上の過失であれば、「業務上過失致傷罪」として「5年以下の懲役又は禁錮刑又は100万円以下の罰金」とされています。 業務上の過失の方が刑罰が重くなっています。
DVや児童虐待
家族であっても暴力は許されません。「教育である」は通じないのです。 周囲が警察に通報する場合や、被害者が通報したり警察に相談して発覚することが多く、家族という関係性から、警察に行った後、「家族なので逮捕されて欲しくない」と主張を覆しても、刑罰処分されることはあります。
解決事例

来所不要、LINE相談OK!
\『刑事事件の無料相談』実施中 /
「もっと早く弁護士をつけておけばよかった」
と後悔される前に一度ご相談ください。
LINE無料相談
( 土日もOK! )
以下のご相談は
お受けしておりません
- 被害者のご相談
- ご家族以外・未成年の方
- 逮捕前・警察から呼び出される前のご相談